スマホの普及で読書する人が減っているのをご存知でしょうか?
2023年の文化庁の調査データから読書量が減っている理由の一番が「スマホや携帯電話で時間がとられるから」。
さらに1ヶ月に1冊も本を読まない人が62,6%で前回調査(2018年)より15,3%増加しています。
文章を読む機会が減ると、自分の脳で考える習慣が減り想像力や論理的思考力などの低下につながります。
今までなんとなく本を読んでいた人も、具体的な効果がわかれば読書に対する取り組み方がおおきく変わります。
この記事では読書の効果をわかりやすく丁寧に解説しています。
最後まで読めばさまざまな読書効果を理解でき、あなたの学習成長に必ずつながります。
・元書店員
・毎年10年以上100冊以上の読書継続
継続力の向上

時間を決める
毎日同じ時間にやることで習慣化していき継続できます。
例えば、昼食後、夕食後、就寝前、通勤時などがとりくみやすい時間帯。
ほとんどの人は1日の余った時間で読書しようとする→仕事が忙しかったり、他の誘惑に負けてしまい結局時間は余らない
三宅香帆さんの著書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」にも大人になってから読書する機会が減ったとあります。
スマホが普及し一人で遊べるSNSやゲーム、ネットフリックスなどの娯楽コンテンツが溢れかえっていることが起因。
読書するためには事前に時間を決めてやることが大切です。
毎日30分読めば
1週間で3,5時間
1ヶ月間で15時間
1年間で180時間
5年間で900時間
10年間で1800時間
アメリカのイウェール大学の調査では 週に3,5時間以上読書をする人は
全く読まない人より向こう12年で約17%死亡リスクが低く平均で2年ほど長生きしている。
繰り返し読む
最初読んだときに気づかなかった新たな発見ができるため。
一回読んだだけだと内容を記憶できないため毎回アウトプットすることを意識する。
理由は印をつけることで記憶に残りやすく、次に読んだときにどこが重要部分かすぐにわかるため。
並行読書とは何か?研究でわかった効果とメリット・デメリットを解説
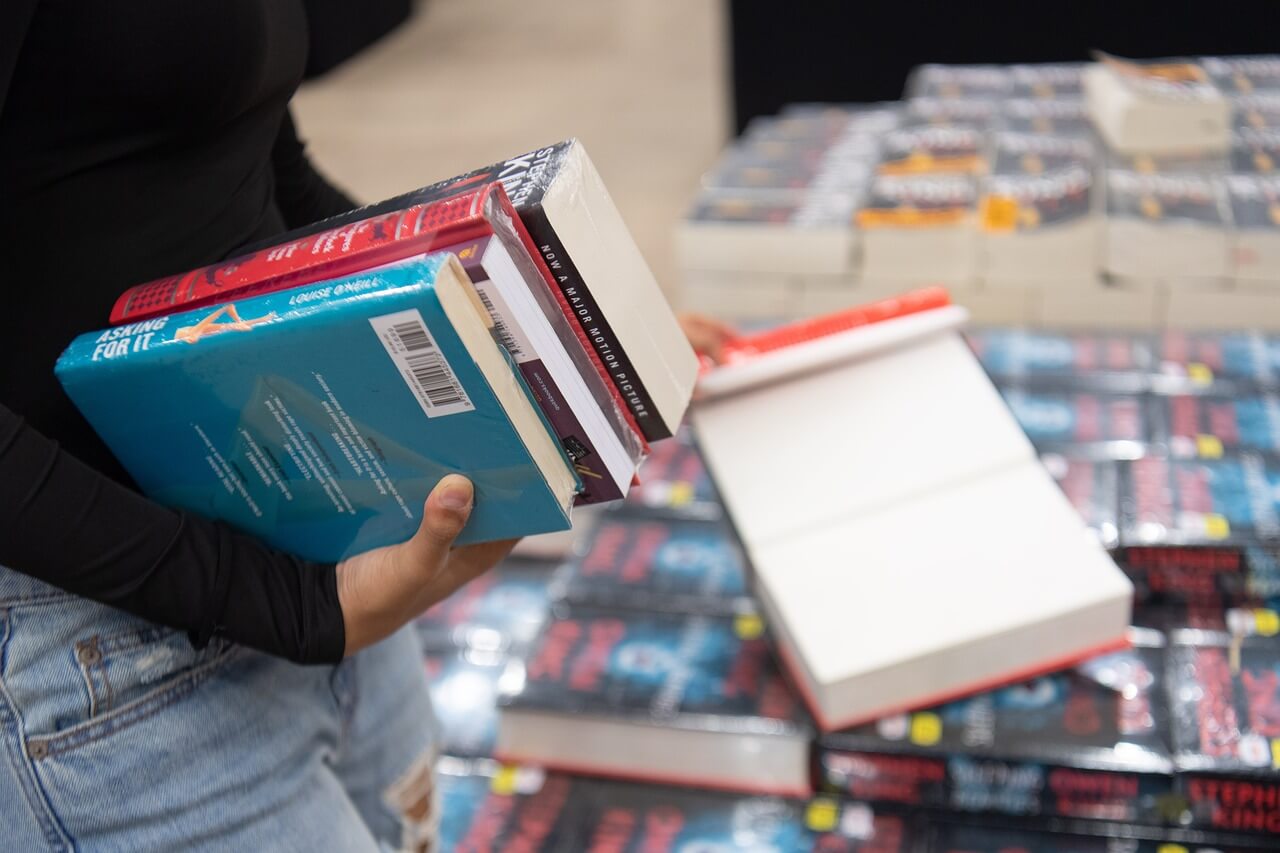
アウトプットのネタになる

本の正確な情報をインプットすることで質の高いアウトプットにつながる。
読んだ本を他人におすすめすることは頭で内容を整理する必要があり高いアウトプットになります。
SNSで投稿する
読んだ本の内容をSNSで発信すればアウトプットになっていろんな人にみてもらえる。
いつでも気軽に自分の感想を情報発信ができるためおすすめ。
メモや日記に書き出す
アメリカのプリンストン大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の共同研究では
講義のときにパソコンでノートをとる生徒よりも手書きでノートをとる生徒は、記憶が定着しやすく成績もよいという結果がでている。
パソコンは見聞きした言葉をそのまま入力していきがちに対して、手書きは自分なりに咀嚼して考えたり要約する必要があるからと研究では考察されています。
想像力が高まる
東京大学大学院の酒井邦嘉教授の「読書は想像力を高める」によると
脳は過去の記憶をもとに想像する。
過去の記憶をもとにして,いくつかの要素を組み合わせることによって,正確な「想像」が可能となる。逆に言えば,一度も記憶した経験がないもの,つまり全く見たことも聞いたこともないものを想像することは難しい。
文章から情景や登場人物の感情や思考を想像して読み進めていかなければならない。
本の世界に没頭しているときは現実とかけ離れた体験をしているため想像力アップにつながる。
文章力の向上
本は一冊が出来上がるまでにいろんな人の目にふれて何度も練り直して作られます。
書籍づくりには大きく分けて編集者、デザイナー、校正・校閲、印刷会社の4つの専門家が関わっています。
引用 幻冬舎ルネッサンス
各専門家がたずさわった文章を読むことでいろんな言葉や表現方法、リズム感など普段目にすることがないものを学べる。
読者に論理的にわかるように書かれていて読み続けることで文章力アップにつながります。
コミュニケーション力の向上

本で学んだ言葉や表現は日常会話でつかえます。
語彙力が増えることで会話としての厚みが増してコミュニケーション力の向上につながります。
多くの本を読みいろんなエピソードを知ることで自分の知らなかった世界がみえてくる。
登場人物の心境を想像したり、気持ちに共感するなどの喜怒哀楽を感じながら文章を通じてコミュニケーション力が養われます。
知識・教養が身につく
わからない言葉や表現方法などを調べて実際につかっていくことで知識が増える。
一つの知識に対して掘り下げて学ぶと周辺の知識が増えて興味が広がっていきます。
本で学んだことを実際に体験するとより学びになって教養につながります。
新しいアイデアが生まれる

本は自分では想像できないアイデアが無限につまっていて仕事や人生のヒントになります。
作家の疑似体験をすることで他人の人生の一部を自分の脳内で生きることができ新たな考えが生まれる。
他人の考えを真似る方が一人で考え続けるより効率的。
本の情報はインターネットと違って誤った内容を書けないため信憑性があり正確な情報です。
一冊の本がお店にでるまでにさまざまな人の目を通すため安心して読める。
要約力の向上
文章を読み解く力がつき要約力が身につきます。
仕事の業務メールや資料を読んだときに何が重要なのか素早く判断する力を養います。
ストレス解消

イギリスのサセックス大学によると
読書によって軽減されるストレスは68%
音楽鑑賞やゲーム、散歩を上回るストレス軽減率です。
読書は短時間でもリフレッシュ効果があることが研究でわかっています。
寝る前に本を読むとリラックス状態になり良質な睡眠につながる。
感受性が高まる
読書によって想像力が刺激され脳が活性化し感受性が向上する。
おすすめは小説で物語の登場人物の心情に注目して読みたい。
論理的思考力が高まる
本は起承転結で構成されており読書することで順序立てて物事を考えられるようになる。
ストーリーや登場人物の関係性、文章のつながりなど考えながら読む必要があります。
本文の展開で「なぜこうなったのか」を考えるシーンもでてくるため論理的思考が鍛えられます。
集中力の向上

本は内容を理解しようとすると集中して読めるようになります。
自分なりの集中できる環境をみつけておくのがポイントです。
静かなところ、心地よいBGMがあるところ、周りの会話が聞こえてくる場所などさまざま。
場所:自宅、カフェ、図書館、電車・バス内
時間:空腹時、食後、運動後、起床後、就寝前
今までの経験を振り返って一番集中できた環境を思い出してみましょう。
会話力の向上
読書中に多くの言葉や表現に触れて吸収できれば、相手に伝えたい内容を適切に伝えることができるようになる。
自分が読みやすいと思える本や著者を探して読むことがポイントです。
失敗のリスクを減らせる

成功者の疑似体験をすることで同じミスを事前に防げる。
過去の失敗を乗り越えた経験を知ることで希望や挑戦する前向きな気持ちになれます。
記憶力の向上
本一冊の情報は膨大で整理して読み進めていく必要があります。
登場人物、背景、ストーリーなど読み進めていくうえで必要な情報が多い。
昭和大の本間元康講師(認知科学)らの研究チームによると
紙の本のほうがスマートフォンよりも内容を記憶しやすいというデータがでています。
読書中、脳の前頭葉の活動はスマホの方が活発だった。脳が過剰に働き、注意力が散漫になっている可能性もあるという。読書中に深く呼吸した回数は、本で平均3・3回、スマホでは同1・8回だった。本間講師は「本ではリラックスして読書できることがうかがえる」と分析している。
読書を効果を高めるコツ

読み終えたらすぐにアウトプットする
樺沢紫苑氏の著書「学びを結果にかえるアウトプット大全」にも書いてありましたが、
アウトプットすることで学んだ内容をうまく整理でき忘れづらくなる。
1冊読書し終わったら以下の3点をする。
・内容を振り返ってメモやノートにまとめる。
・他者にどんな本なのか簡潔に伝える。
・書評サイトやSNSに投稿する。
人に話すことは相手にわかりやすく伝えようとするため論理的思考力が働く。
SNS投稿は文脈や要約力、語彙力がないとうまく伝わらないため文章力が磨かれる。
何度も読み返す
人の記憶は時間が立つほど忘れていきます。
「エビングハウスの忘却曲線」の研究では
20分後には42%
1時間後には56%
翌日には74%
翌日には約7割以上を忘れているため反復が必要です。
読んでいるときにマーカーでラインを引いたり、直接書き込む。
重要だとおもった箇所に印をつけたり、感じたことを書き込むことで集中して読める。
読み返した際に重要箇所がすぐにわかる。
読書を習慣化させる方法

毎日同じ時間でよむ
事前に時間を決めることで他のことをせずにすぐに読書が始められる。
・通勤時
・昼食後
・夕食後
・就寝前
食事は日によっては時間がズレたりすることが考えられますが、
通勤時の電車やバス、就寝前の時間であれば変動が少なく(人によりますが)おすすめです。
ワクワクする本を選ぶ
興味あるジャンルやテーマの本であれば、自発的に読めるようになります。
常に本が読める状態にする
カバンに本を入れておく。
荷物を増やしたくない人はスマホの読書アプリでいつでも読める状態にする。
アマゾンアプリのkindle unlimitedは読み放題サービスがありおすすめです。
ちょっとしたスキマ時間でも読むことが習慣化させるコツです。
とくに移動や待ち時間を有効につかうのがおすすめ。
図書館の利用
本を無料で借りて読むことができるためお金の心配をせずに読めます。
返却期限があることで読もうとする意識が働く。
朝と夜どちらがよいか?

朝がおすすめ
メリット
・頭がスッキリしていてむずかしい本でもよめます。
・仕事前などであれば時間制限があって集中できる。
・読んだ内容をその日会う人に話したり教えたりすることができます。
・早朝なら周りの邪魔(仕事TEL、メールなど)が入りづらく集中できる。
デメリット
・短時間しか読めない。
夜
メリット
・読書してリラックスした状態で眠りにつける。
・夜は朝に比べて時間的制約がないぶん長時間読める。
デメリット
・疲れていて難しい本がよめない可能性がある。
・ダラダラ読んでしまい内容が頭に入ってこない。
どれぐらい読めばよい?

一ヶ月に一冊
本のジャンルによりますが文庫小説で一冊300ページ前後のものが多いので1日1時間10ページ×30日で一冊。
2023年の文化庁の読書データからは一ヶ月に一冊も本を読まない人が約6割を超えるため、月1冊よんでいれば平均を超えているので十分です。
重要な点は読んだ数ではなくて質です。
やみくもにたくさんの本を読んでも内容を全く理解していなかったり、すぐ忘れてしまうと時間をかけて読んだ価値がなくなります。
読書する際は内容を誰かに話そうと意識しながら読むとより集中することができます。
大人におすすめのジャンル

小説
他人の人生を疑似体験できて、現実とは違う世界へ没入できます。
多くの登場人物同士のやりとりで感受性を磨かれたり思考や考え方を知れて価値観が広がる。
ストーリーの移り変わりを理解するための論理的思考力、想像力がきたえられる。
本文でつかわれる表現方法が学べて語彙力や文章力アップにつながる。
歴史
過去に起こった失敗や叡智を知り現在に活かすことができる。
異なる文化や地域の違いを知り教養を深められる。
偉人がしてきたことを参考にして自分の成長につなげる。
マンガ
ビジュアルでわかりやすく楽しませることができて老若男女が楽しめる。
人生におけるさまざまな示唆を与えてくれる。
くすっと笑えたり、感動したり、泣いたりと感情移入しやすいジャンルです。
例えば、スポーツマンガであれば試合に勝つための努力、熱い友情、強力なライバルなどがいて主人公が成長していく。
マンガを読んだキッカケでスポーツを始めた人も多いはずです。
スポーツだけでなく仕事やプライベートでも応用してつかえる名言です。
自己啓発書
能力の向上や精神面での成長に効果的です。
読むことでやる気やモチベーションの向上、自己成長の手段としておすすめです。
まとめ(読書の効果15)
①継続力の向上
②アウトプットのネタになる
③想像力が高まる
④文章力の向上
⑤コミュニケーション力の向上
⑥知識・教養が身につく
⑦新しいアイデアが生まれる
⑧仕事力の向上
⑨ストレス解消
⑩感受性が高まる
⑪論理的思考力が高まる
⑫集中力の向上
⑬会話力の向上
⑭失敗のリスクを減らせる
⑮記憶力の向上
読書したらすぐにアウトプットすることが重要です。
本の内容をまとめたり、他の人に伝えたり、情報発信することなどがアウトプットに該当します。
これらをすることで読書15のメリットが自分の血肉になっていきます。
読む時間帯は固定化させて習慣化させるのがコツです。
自分の興味のある本を選んで短時間からでもスタートしてみましょう。
メリットだらけの読書はあなたの今後の成長におおきく役立ちます。
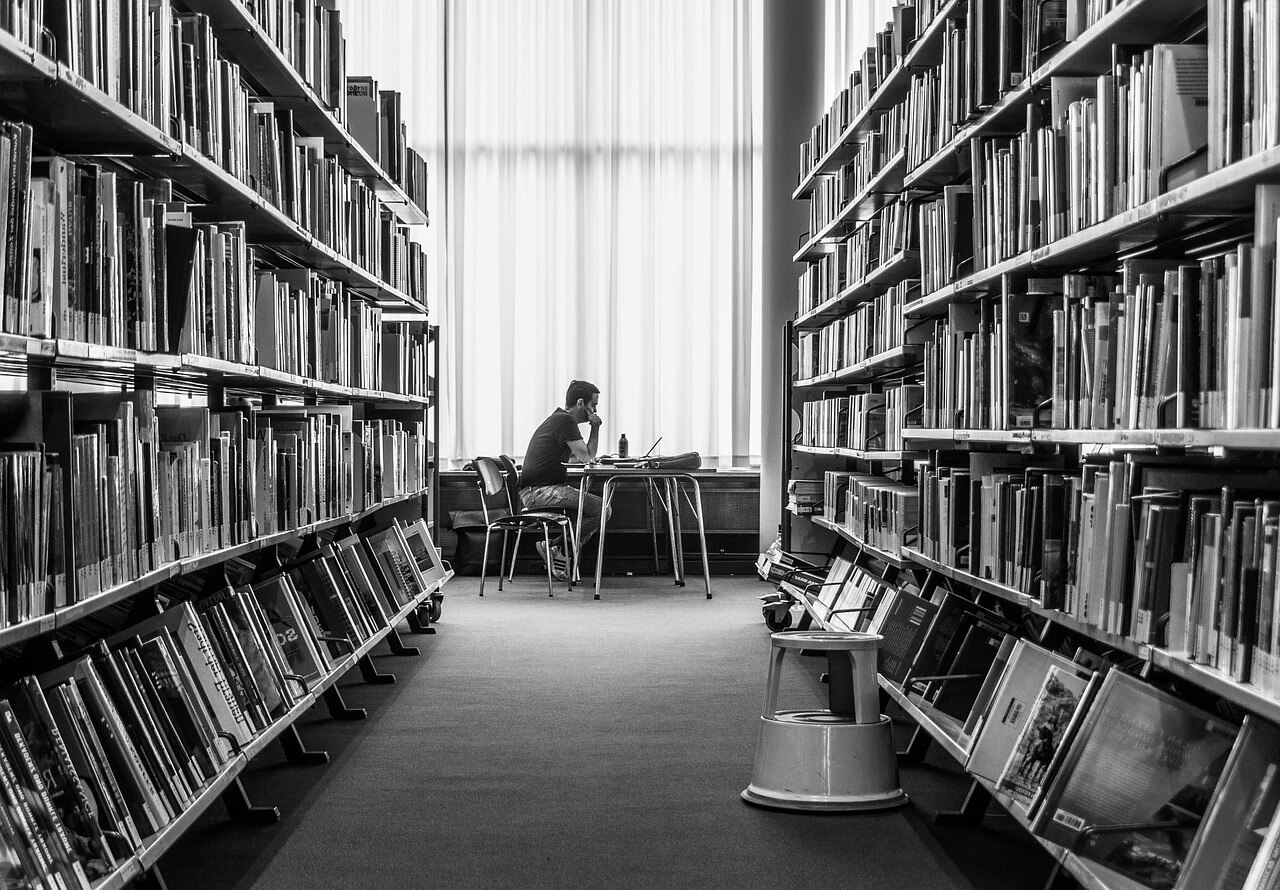


コメント