お金に関する知識を基礎から学びたい人
昔お金について学んだ経験はあるけど最近学んでない人
1章 お金の計画の基本
お金の3つの役割
①交換の手段…買い物
②価値の保存…お金そのものの価値 例 1万円札は1万分円の価値
③価値の尺度…サービスやモノの価値をお金で表すこと 例 スマホ端末代金15万
インフレーション…モノやサービスの価値が上がること
デフレーション…物の価値が下がること
考えられる3つの原因
・世界的なコロナ禍からの回復での原材料の価格上昇
・ウクライナ侵攻での小麦やエネルギーの価格上昇
・円安
この3点が合わさることで物価が上昇する
要するに
モノの値段が上がると消費者は買い物を控える
↓
買い物をしてくれないと企業の売上が下がる
↓
売上が下がると社員の給料を上げられない
日本の物価は海外と見比べてもまだまだ安いため今後も上がり続ける
私たちがやるべきこと
企業側がよりよいモノやサービスを作る努力をして買ってもらう努力が必要
価値が伝われば買い物をしてくれるようになり会社の売上がアップ
そのためには一人ひとりの働く人が頑張って仕事をする必要がある
個人でできることを具体的にすると
より高いスキルを目指して資格をとって仕事に活かす
自分の仕事の得意分野を見つけてエキスパートして働く
若い人や新人に仕事を教えて会社全体でレベルアップ
2章 お金とキャリア設計の基本
仕事で価値のある存在…仕事で経験してきた知識、スキル、コミュニケーション力などの能力(人的資本)が続けていくうちに高まり他より必要とされる存在
人的資本を蓄積することが大切
蓄積するには自己啓発が必要
例えば社内昇進、資格所得、副業でスキルアップ、仕事で有効な習い事をする
結果→いろんな会社からオファーがきやすくなり自分で取捨選択できる
3章 就職、転職、企業の基本
個人事業主…個人でビジネスを行うことで開業届を届けるだけでなれる
会社…正式な手続きが必要で登録されれば法人となる
現在では会社にいながら空いた時間で個人事業主として働く人が目立つ
パーソナルトレーナー、清掃サービスなどの小規模ビジネスをする人が増加
一つの会社の仕事だけでは給料アップにつながらなったり
より高いスキルを目指してやる人が高まっている
4章 貯金と銀行の基本
貯金3つの理由
①将来の支出に備える
②人生の大きな目標に備える(留学、起業、結婚など)
③緊急時に備える(病気、ケガ、老後など)
貯金の仕方
・お金が入れば貯金分を別にする(天引き、自動積立)
・切り離し(生活費と貯蓄用)
・すぐに使えないようにする(銀行のすぐ引き出せない口座)
銀行は何のためにあるか?
個人やビジネスからお金を預かり、貸すという機能
貸す機能は住宅ローン、自動車ローン、クレジットカード利用といった
約束の期日までに返すという取り決めがある
2種類のローン
・取引手数料…ローン契約時のみ払う
・利息…ローンが終わるまで払う
ビル・ゲイツは1994年に「銀行機能は必要だが、今ある銀行は必要なくなる」と発言していた。
世界のコロナの影響やスマートホンの影響で非対面でのやりとりが
当たり前になり銀行に行く機会は減っている
アプリだと銀行窓口やATMにいく手間さえ省ける
今後の銀行のあり方が変わってくることは間違いない
インターネットバンキングを利用すれば、銀行の窓口やATMに行かなくても、自宅や外出先などで、銀行の営業時間を気にすることなく振込や残高照会などをすることができます。このような便利さから、インターネットバンキングの利用は急速に拡大しています。総務省HPより
5章 予算と支出の基本
予算を立てる…すべての収入と支出をリスト化する
①過去の1ヶ月分の収入と支出の把握
②向こう1年の支出と収入を予測する
自分は何にどれだけお金をつかったかの把握が必要
つかいすぎたところを抑えていくきっかけになる
給与明細書を細かく確認
給与明細に控除と記載されているところ
所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料など
6章 信用と借金の基本
ローン…一定の条件でお金を貸すこと
お金を借りたら利息も払わなければならない
利息とはお金を借りるコストのこと
貸し手が利息を要求する3つの理由
①貸したお金が返ってこないかもしれない可能性
②貸しては利息がもらえない貸す意味がない
③お金を貸すというビジネスモデルを運営するお金が必要
7章 破産の基本
破産…借金免除、大幅に減額される法的手続き
貸した側…損をする
借りた側…資産と収入を維持でき元の生活に戻れる
8章 投資の基本
投資…価値あるものを一定期間もっていて後になってそこから金銭的な利益を得るリターンあり
2つのリターン
①投資したそのものの価値が上がること
②投資したものが生み出す利益や配当
投資を長期で考えるのがコツ
とくに複利効果をつかうと自動的にお金が増える
9章 金融詐欺の基本
ピラミッドスキーム…「絶対に儲かる投資がある」といって会員を集め大儲けしているふりを見せる方法
詐欺を見分ける2つ方法
①リターンが高すぎる
②運用成績が安定しすぎている
情報弱者はひっかかりやすい
10章 保険の基本
保険…損失のリスクを移転させる契約
契約者は保険料を払う
代わりに
損失があったときに保証を受けられる
テレビCMでもおなじみのがん保険
「万一のリスクに備えて安心」はよく耳にする
11章 税金の基本
税金…国や地方自治体から強制的に徴収されるお金
お金を稼ぐ人は自動的に納税の義務を負う
税金の発生する主な3つの機会
①資産を所有している 自動車や不動産など
②所得がある 自分で稼いだお金
③買い物したとき 消費税として発生
税金は何につかわれているか?
行政のサービス
医療、教育、公共事業(建物、道、港、トンネル)
消防、警察、裁判所、刑務所
私達のみえないところでつかわれている
12章 社会福祉の基本
失業保険…失業者に対しての金銭的な支援
労災保険…ケガや病気による損害を補償する制度
失業保険の受給日数は細かく定められています
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上 45歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
*出典:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
13章 法律と契約の基本
契約…2者かそれ以上の当事者による合意
買い物をする(売買契約)
スマホの使用(携帯キャリア会社との契約)
契約すると義務が生じ当事者同士で価値あるものを交換することになる
14章 老後資産の基本
貯金は老後ではなく働いて稼いでいるときにするべき
老後の資産づくりは早く始めるほど大きな複利効果が期待
金融庁の報告書では
「老後の30年間で約2,000万円が不足する」と発表あり
・今から少しづつ倹約して生活する
・少しでも長く働く
・年金をもらうのを遅らせる
65歳から支給されるが遅らせることで給付額が上がる
・長期積立投資をやっていく
iDeCoやNISA
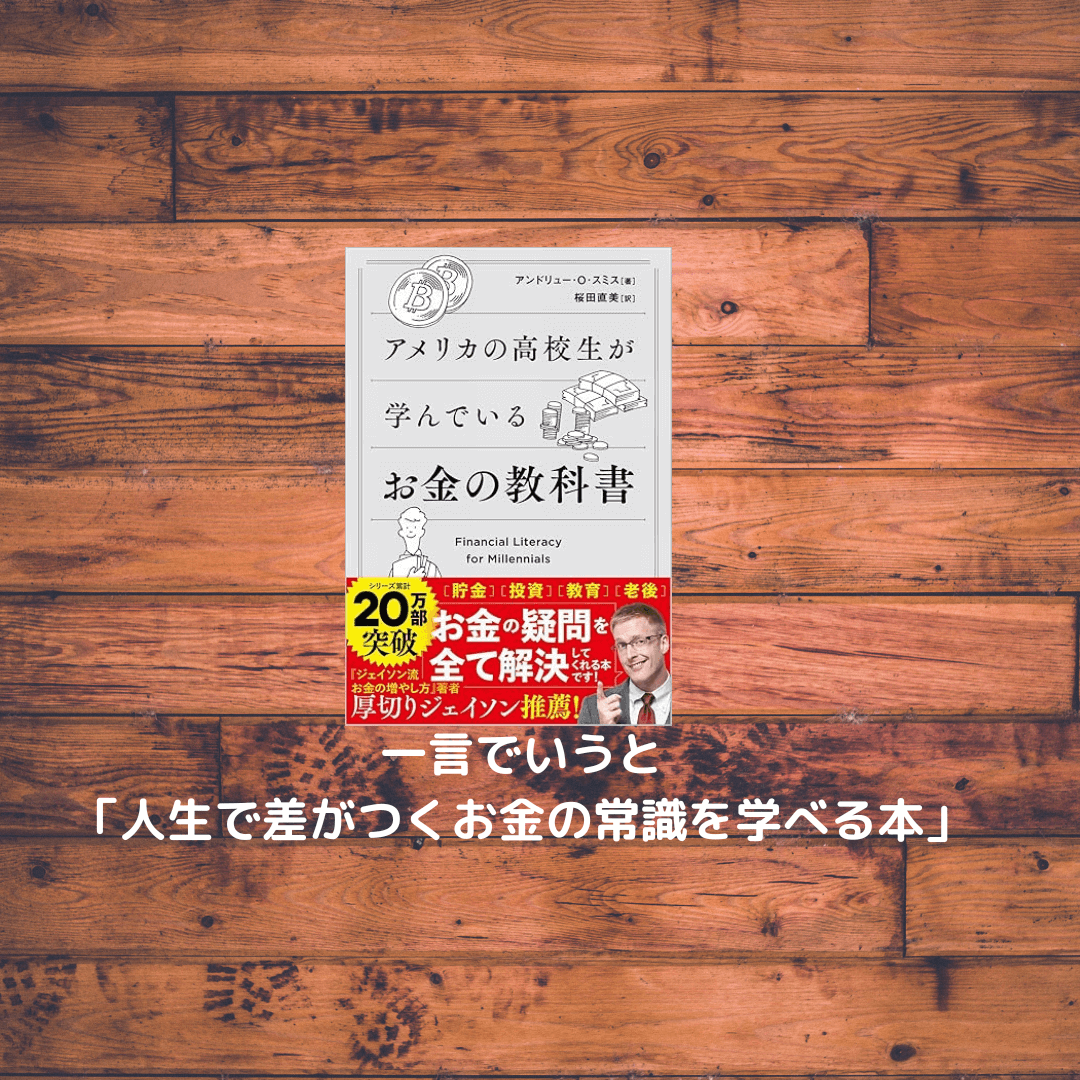

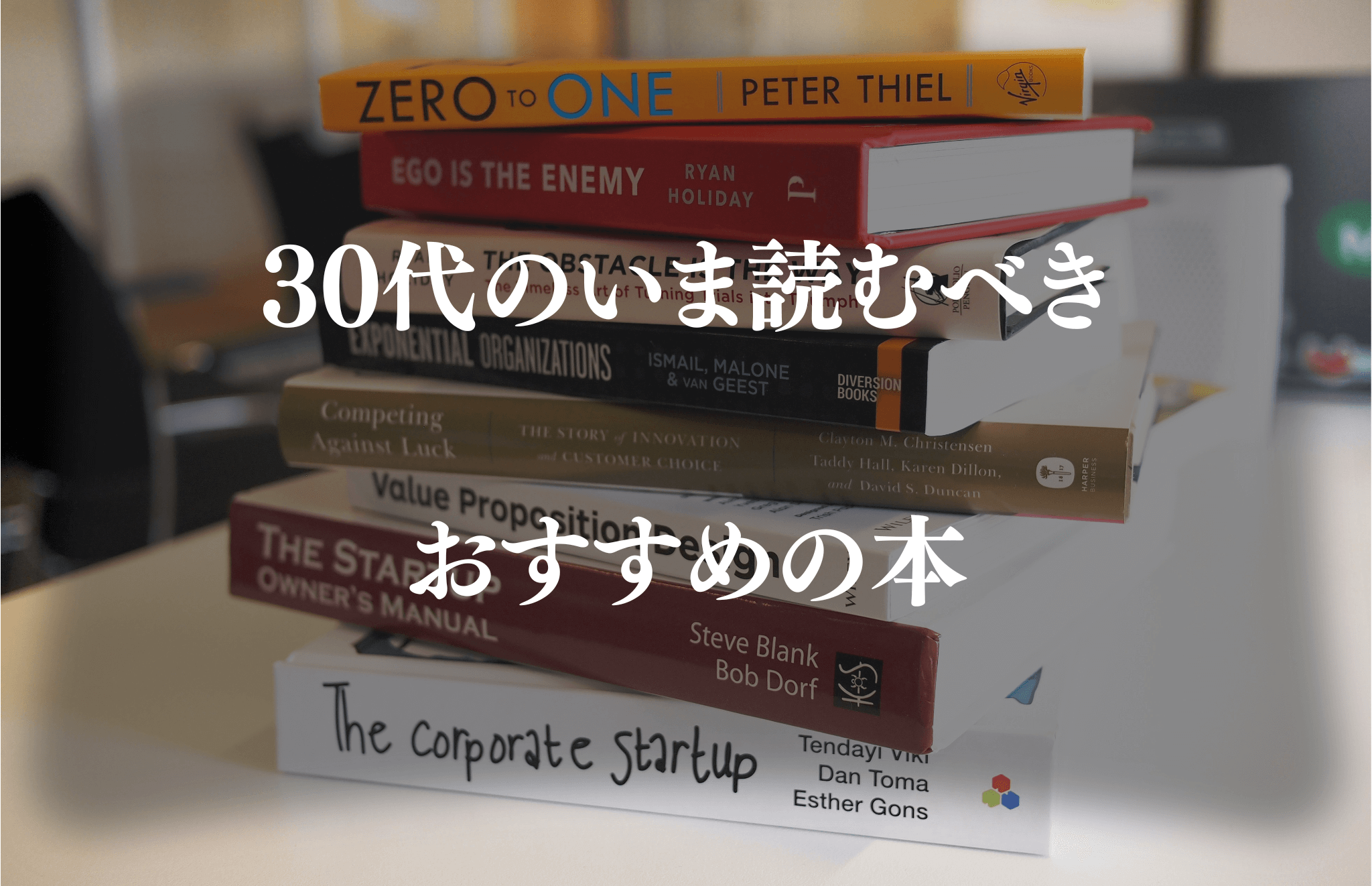

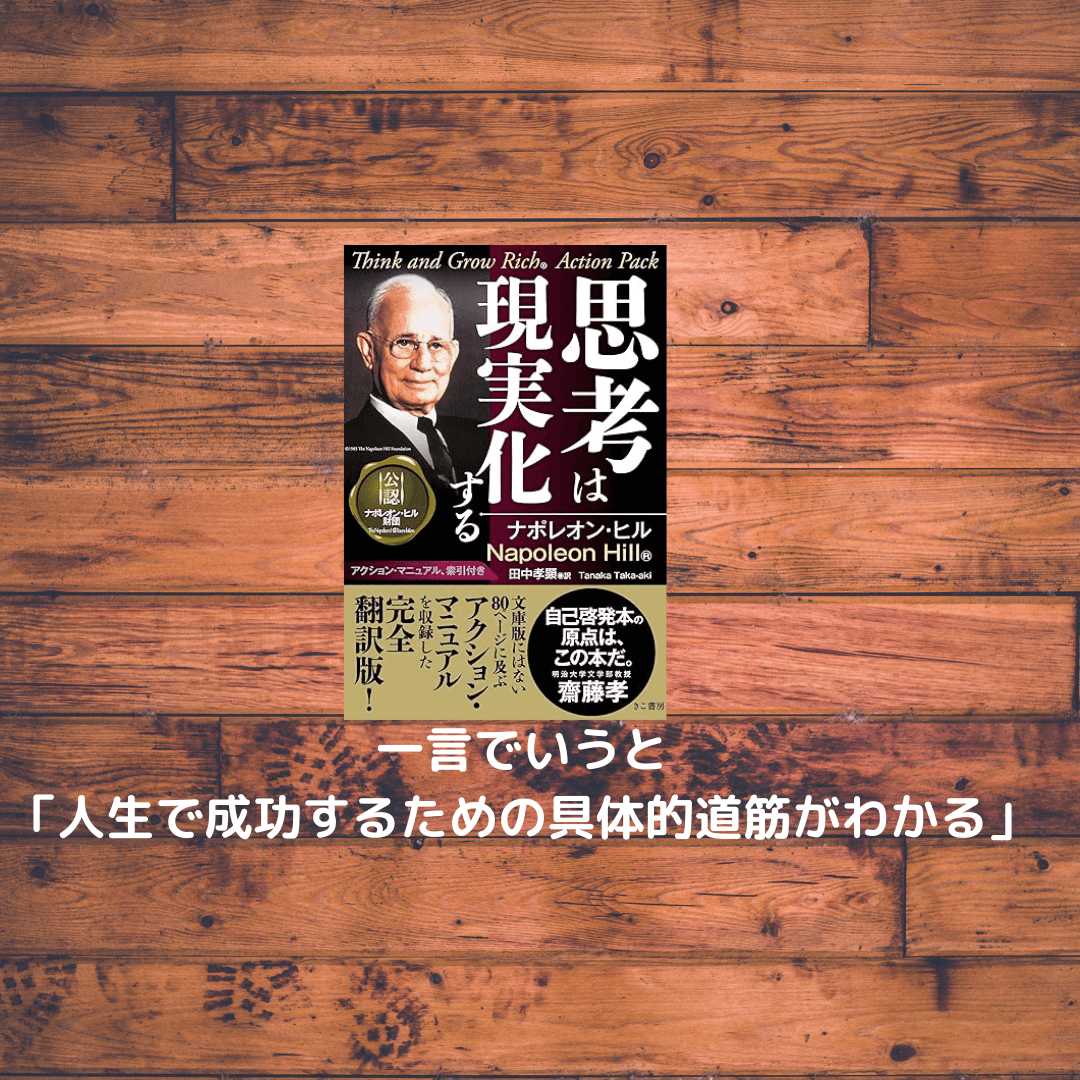
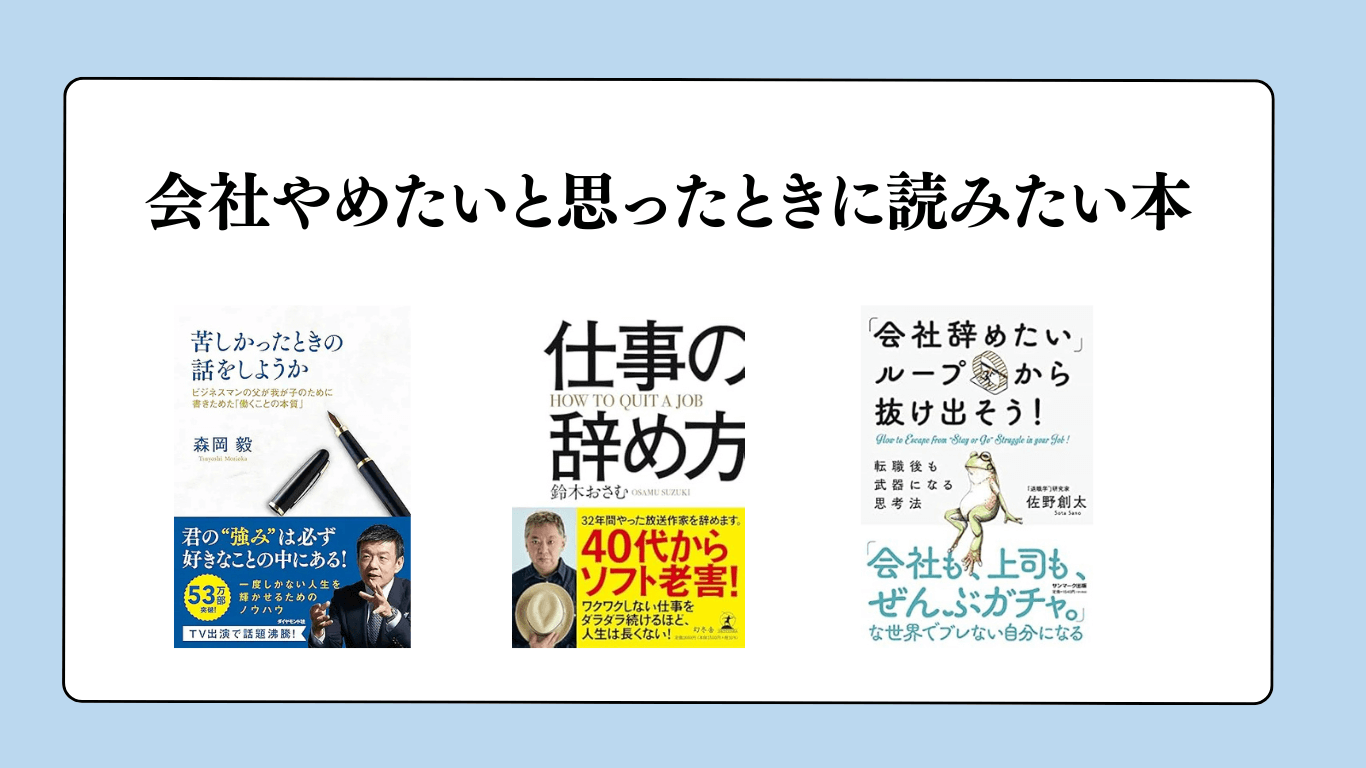

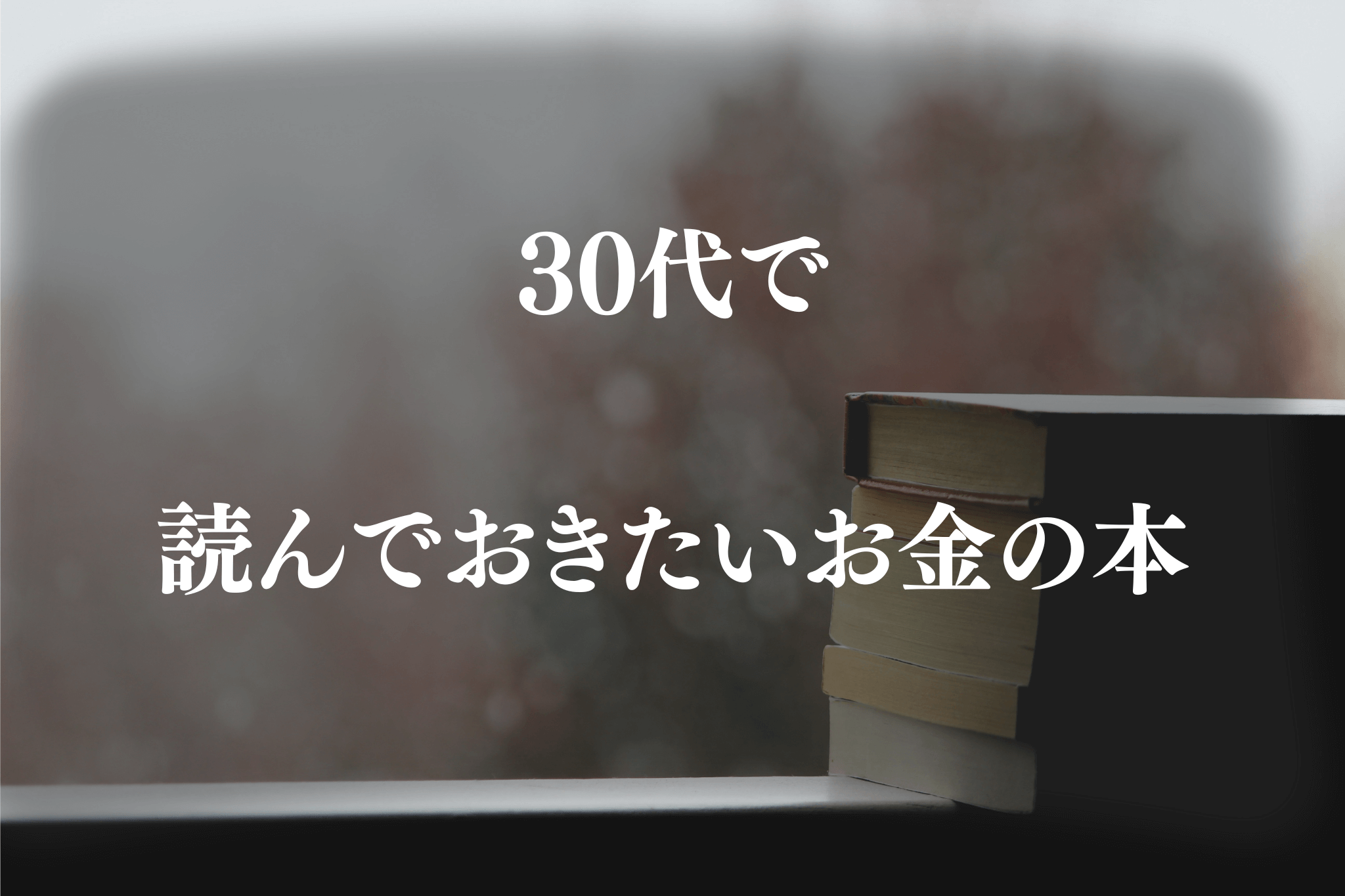
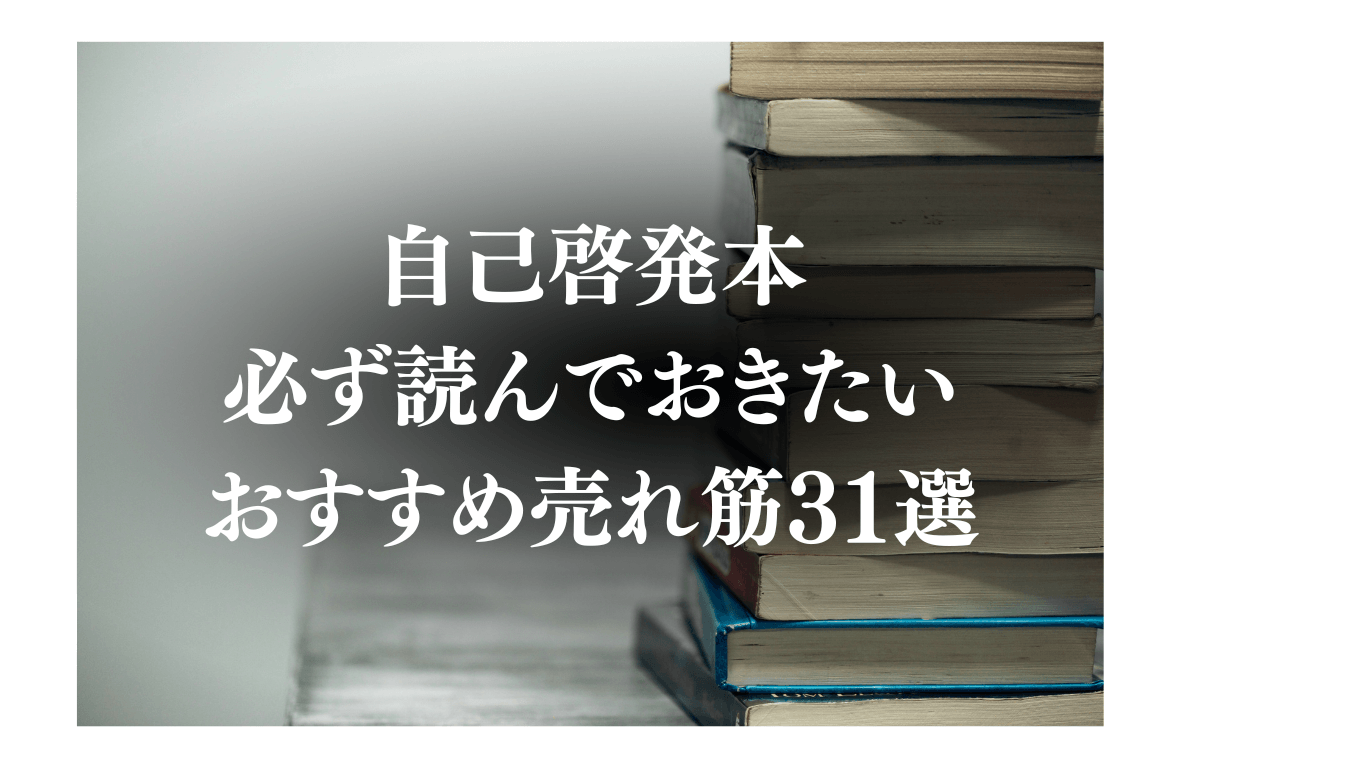
コメント